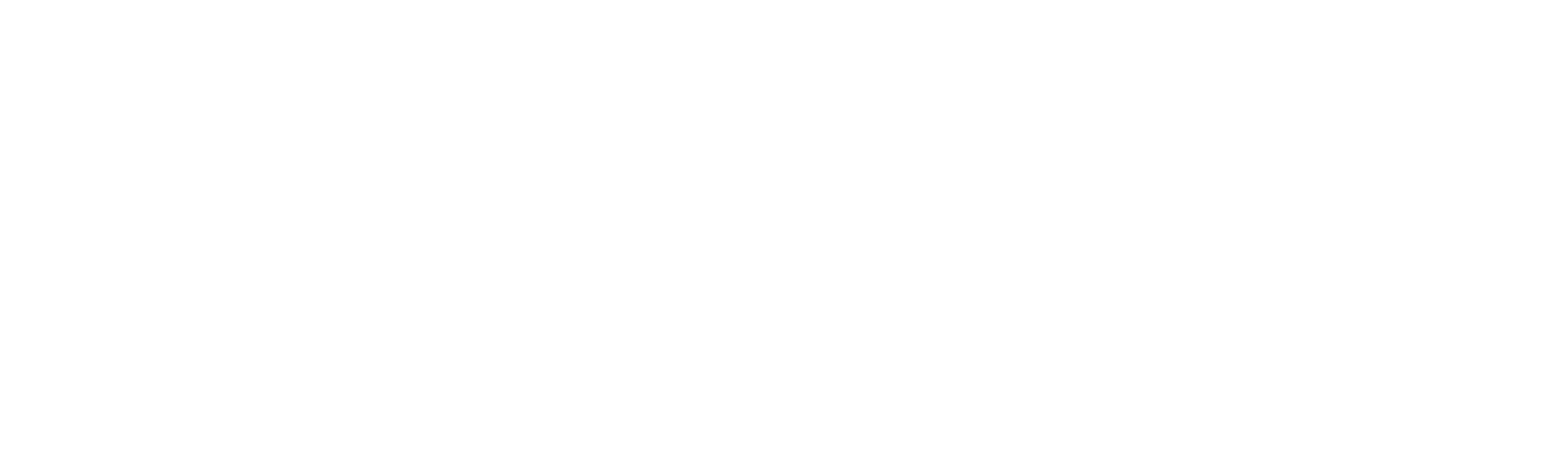『徒然草』とは?
『徒然草』は兼好法師によって書かれた随筆で、正確な成立年は不明ですが、鎌倉時代末期に成立したとされています。「つれづれなるままに、日ぐらし…」で始まる冒頭はとても有名です。日本三大随筆の一つで、仏教的な無常感を軸としながら、生活や趣味、逸話など幅広い話題を取り上げています。
日本三大随筆とは、清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』、兼好法師の『徒然草』のことを言います。
長短様々の章から成る243段の構成ですが、今回は名言や人生の教訓、大事にしたい考え方が含まれる章段を独断と偏見でピックアップして紹介します。要約は分かりやすく内容をまとめたもので、全文訳ではありません。
仁和寺にある法師
少しのことにも、先達はあらまほしき事なり(52段)
◆この段の要約
仁和寺にいたあるお坊さんは、歳を取るまで石清水八幡宮を拝んだことがなかったので、心残りに思っていた。ある時、思い立って徒歩で参詣したが、岩清水八幡宮の付属の神社である極楽寺と高良神社だけ拝んで、これだけのものと思って帰ってきてしまった。
帰ってから仲間に向かって「長年の間思っていた事をついにやり遂げた。噂に聞いていた以上に尊いものであった。それにしても、お参りしている人々がみな登山をしていたので、何があるのだろうかと知りたかったけれど、神様に参拝するのが本来の目的だと思い、山頂までは見てこなかった。」と語った。
どんな些細なことでも、その道の先導者はあってほしいというものである。
吉凶は、人によりて、日によらず
「吉日に悪をなすに、必ず凶なり。悪日に善を行ふに、必ず吉なり」と言へり。吉凶は、人によりて、日によらず。(91段)
◆この段の要約
世間では「赤舌日」は何をするにも良くない日だとされているが、昔の人はこれを忌み嫌ってはいなかった。この頃は誰が言い出したのか、この日に言ったことや、したことは叶わず、得たものは失い、企てたことは失敗するというのは愚かである。吉日に同じことをして、上手くいかないのを数えたら同じになるだろう。
この世の中は無常変易であり、全てのことは変化する。人の心は定まらず、物事も全て留まることはない。この原理を知らないのである。「吉日に悪事を成せば、必ず凶である。悪い日に良いことをすれば常に吉である。」吉凶は、その人自身の心がけによるもので、日の良し悪しによるものではない。
 |
兼好さんの遺言: 徒然草が教えてくれる、わたしたちの生きかた 新品価格 |
高名の木登り

過ちはやすき所になりて、必ずつかまつることに候ふ。(109段)
◆この段の要約
有名な木登りの名人が、人に高い木の枝を切らせた時、明らかに危険な高いところでは何も言わず、家の軒くらいの高さに降りてきたところで、「怪我をするな、注意して降りろ」と声を掛けた。
それを見ていた兼好法師が理由を問うと、名人はこう答えた。
「高くて危ないところは、自分で用心するので何も申しません。失敗は安全な所になってから必ずしてしまうものでございます。」と。
美について

花は盛りに、月は隈なきをのみ、見るものかは。雨にむかひて月を恋ひ、垂れこめて春のゆくへ知らぬも、なほ、あはれに情け深し。咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ、見所多けれ。(137段)
◆この段の要約
花は満開の時に、月は満月だけを見るのだろうか(いや、そうではない)。雨の中、雲の向こうの月を思うのも、簾をおろして閉じこもっていて、春の様子が分からないとしても、やはりしみじみとして趣がある。まだ咲いていないが蕾が膨らむ梢、花が散ってしまって庭一面を覆う様子など見どころはたくさんある。
花が散り、月が傾くのを惜しみ慕うのは当然だが、物事の道理がわからない人は「この枝もあの枝も散ってしまった。もう見どころはない。」と言うものだ。どんなことでも、始まりと終わりにこそ趣がある。男女の恋愛も、常に会って親しくしていることだけでなく、成就しなかった恋の悲しさを思い、叶わなかった約束を嘆き、長い夜を一人で明かしたりなどこそ、恋の趣というものである。
死期は序を待たず

四季は、なほ、定まれる序あり。死期は序を待たず。死は、前よりしも来らず。かねて後に迫れり。人皆死ある事を知りて、待つことしかも急ならざるに、覚えずして来る。沖の干潟遥かなれども、磯より潮の満つるが如し。(155段)
◆この段の要約
四季には春・夏・秋・冬の決まった順番がある。死期は順番を待ってはくれない。死は、前から来るとも限らず、すでに背後に迫っている。人は皆、死があることを知りながら、それでも今日明日のことではないと思い込んでいる。ところが死は突然不意にやってくる。それはちょうど、沖の干潟が遥か遠くまで水に浸かっていないから潮が来るのはまだ先だと思っていたら、背後の磯の方から潮が満ちてきているようなものだ。
秋の月

秋の月は、限りなくめでたきものなり。いつとても月はかくこそあれとて、思ひ分かざらん人は、無下に心うかるべき事なり。(212段)
◆この段の要約
秋の月は限りなく素晴らしいものだ。それを、月はいつもこういうものだと、他の季節の月と区別が付かない人は、どうしようもなく情けない。
まとめ
今回ご紹介したのは『徒然草』のごく一部です。無常感を基軸に、だからこそ今を大切に、楽しもうという気持ちにさせてくれます。
時代を超えて私たちの胸に響く言葉の数々に出会うことができる『徒然草』を、ぜひ読んで見てください!
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |