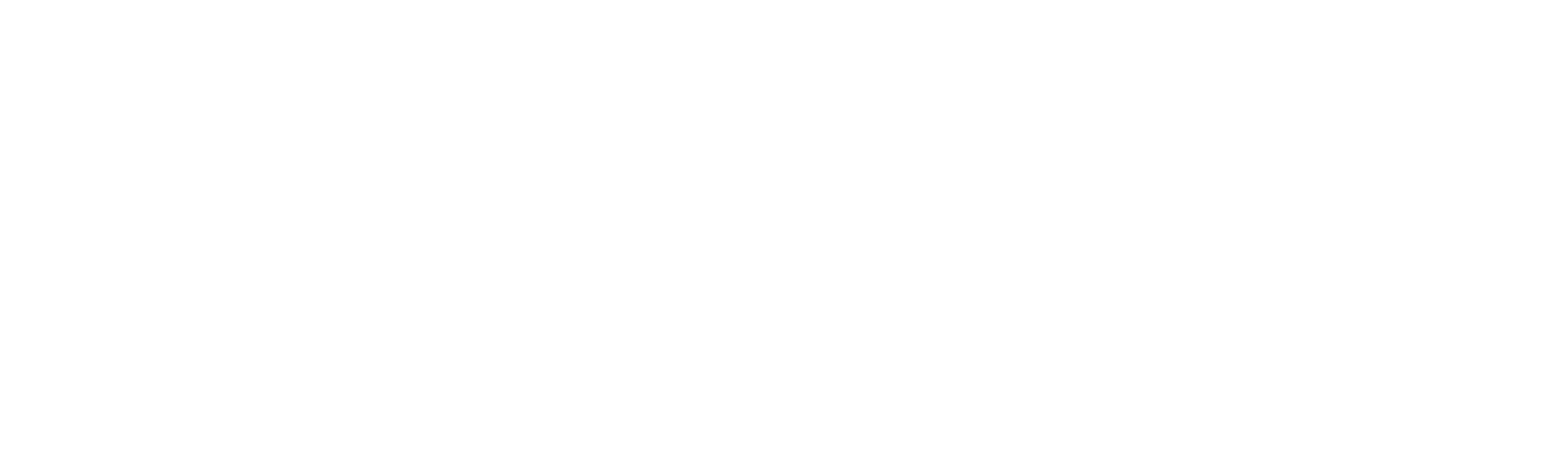九州・沖縄では全部で16のお城が日本100名城に選定されています。今回はその全16城の見どころを徹底解説します。お城にまつわる歴史や注目ポイントを事前に知っておくとお城観光がもっと楽しくなること間違いなしです!
福岡城(福岡県)

福岡城は黒田長政によって江戸時代の1607年に築城されました。福岡城という名前は黒田氏のゆかりの地である備前国邑久郡福岡(現在の岡山県)に由来していて、現在の県名にもなっています。
現在は城跡一体が舞鶴公園として整備されており、桜の名所として多くの観光客がお花見に訪れます。有料駐車場がありますが、桜のシーズンは大変混み合うため、公共交通機関でのアクセスをおすすめします。駅から徒歩10分ほどで行くことができます。
天守が建てられたという事実は確認できていないものの、仮に天守が建っていたとすると熊本城のそれと同規模のものと推測されます。天守台からは、城内に咲き誇る桜と福岡市内のビル群を見渡すことができます👇

👇の南丸多聞櫓は1607年に建てられましたが、現存するのは1853年に再建されたものです。

大野城(福岡県)

大野城市の名前の由来にもなっている大野城は、今から1300年以上前の663年に起きた白村江の戦いの後、唐・新羅からの侵攻に備えて築城された山城の一つで、水城や基肄城と共に大宰府の防衛ラインを形成していました。
大野城の見どころは1,300年以上も前に築かれた百間(ひゃっけん)石垣で、全長は150mと城内最大規模を誇ります。大野城のある四天王寺山は頂上まで車でいくことができ、山頂からは大宰府方面を一望することができます。

1,300年以上も前の城のため当時の建造物は残っていませんが、歴史を感じる石垣が魅力のお城です。
名護屋城(佐賀県)

佐賀県唐津市にある名護屋城は、豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に際し急ピッチで築城されたお城です。全国から160もの大名が集まったと言われており、城跡の周りには各大名の陣地が確認できます。これらは「名護屋城跡並陣跡」として国の特別史跡に指定されています。本丸天守台跡からは玄界灘を見ることができます。
江戸時代には城が脅威とならないよう破却されましたが、名護屋城ではそのように意図的に壊された石垣も見どころの一つと言えます。

吉野ヶ里遺跡(佐賀県)

佐賀県にある吉野ヶ里遺跡は弥生時代の大規模な環濠集落の遺跡です。弥生時代といえば稲作が始まり、定住文化が根付いた時代ですが、吉野ヶ里遺跡からは土器や石器、農具や青銅器などが多数発掘されています。2023年には弥生時代後期のものと思われる有力者の石棺墓が発掘されています。
遺跡なのに100名城?と思われるかもしれませんが、外敵から集落を守るための城柵や環濠、辺りを見渡すための物見櫓などを見ると、城がなぜ生まれたのかを想像せずにはいられません。そんな、城のルーツを感じることができるのが吉野ヶ里遺跡の魅力です。
吉野ヶ里遺跡は歴史公園として多くの建物が復元され、当時の暮らしに思いを馳せることができます。園内は広大なので、時間に余裕を持って訪れることをおすすめします。

佐賀城(佐賀県)

佐賀城は江戸時代初頭の1602年に完成し、外様大名の佐賀藩鍋島氏の居城でした。佐賀城下は福岡県の小倉から長崎までを結ぶ長崎街道が通り、宿場町としても栄えました。
佐賀10代藩主の鍋島直正は、藩校の弘道館を充実させたり、長崎防備のため反射炉をつくらせるなどの藩政改革を行いました。弘道館で学んだ人物としては、副島種臣や江藤新平、大隈重信などがおり、幕末から明治新政府で活躍する人物を輩出しています。
写真は鯱の門と天守台に繋がる続櫓で、国の重要文化財です。門をくぐった先には佐賀城本丸歴史館があり、本丸御殿の一部が復元されています。
佐賀空港から車で20分、吉野ヶ里遺跡から30分の所に位置します。

平戸城(長崎県)

平戸城は三方を海に囲まれた平山城で、江戸時代の平戸藩松浦氏の居城です。全国的にも珍しい山鹿流という山鹿素行の兵法に従って建築されました。
天守閣からの眺めが素晴らしく、平戸瀬戸に突出した立地を体感できます。
廃藩置県で廃城となりましたが、北虎口門と多聞櫓が現存しています。模擬天守も建造され、平戸城のシンボルとなっています。

島原城(長崎県)

島原城は松倉氏によって1618年から7年かけて築き上げられました。一国一城令(1615年)が出された後に新たに築城が許された例は少なく全国的にも珍しいですが、これは幕府がキリシタンが多く住む島原を重要視していたためと言われています。雲仙岳東側の麓に位置し、天守からは有明海を望むことができます。
現在は天守閣は資料館として、島原城の歴史やキリシタン資料などを展示しています。
見どころは今も残る石垣と堀で、石垣は幾重にも折れていますが、これは死角をなくし敵を攻撃しやすくする戦略的な構造です。

駐車場は城内にありますが、お堀の外に出て本丸の南東側から見ると強固かつ優美な島原城の姿を見ることができます。
城下にはかつて鉄砲組の移住地として整備された武家屋敷が建ち並び、今も往時の名残を留めています。元々は生活用水であった水路が武家屋敷の中央を流れ、鯉が泳ぐ姿と歴史的な町並みが調和してとても風情があります。ぜひ島原城と合わせて観光したいところです。
松倉氏が入封して島原城が築城される以前は、南島原にある原城が拠点でした。島原・天草一揆の主戦場となった場所で、あわせて訪れてみてください。

熊本城(熊本県)

1607年に加藤清正によって築城された名城で、築城に際し清正が銀杏の木を植えたことから別名を銀杏城とも言います。お手植えの銀杏は西南戦争で焼失しましたが、根本から新芽が成長し、今も大銀杏として本丸前に堂々と聳え立っています。
見どころは鉄壁の石垣で、曲線を描くように上の方は反り返りが激しくなり、忍者でさえも登ることができないことから武者返しと呼ばれています。熊本銘菓の武者がえしはここから取られています。
本丸上段西側にある二様の石垣は年代の異なる石垣が重なっています。なだらかな方が加藤清正時代の石垣で、急峻な方は加藤清正の息子・忠広の時代に増築されたものと推測されています。(細川氏の増築とする説もあります)

2016年の熊本地震で甚大な被害を受け、櫓や石垣が倒壊しました。今も復旧工事が行われており、天守閣は復旧が完了したものの、その他の櫓などを含めると完全復旧は2052年になる見込みです。(2025.2現在)

人吉城(熊本県)

鎌倉時代から幕末までの700年近い年月を相良家が治めていました。球磨川と胸川を天然の堀としてつくられています。

石垣の上部にはね出し(武者返し)が取り付けられていて、これは幕末の城に見られる珍しい西洋式の形態です。
2020年の洪水の被害を受け、現在も修復工事中で一部立ち入り禁止の箇所もありますので、留意が必要です。
岡城(大分県)

滝廉太郎が作曲した「荒城の月」のモデルとしても有名な岡城。見どころはなんと言っても断崖絶壁に築かれた高い石垣です。
竹田市の海抜325mの台地にそびえ立つ岡城からの眺望はとてもよく、阿蘇山やくじゅう連山を望むことができます。桜の名所としても知られていますが、紅葉の時期もオススメです。

大分府内城(大分県)

大分県大分市の中心部にある府内城は、1597年から築城が開始し、関ヶ原の戦いの後に完成しました。大分川と住吉川の河口部に築かれ、当時は北側が海に面していました。当時は船着場でもあったことから、府内城は別名荷揚城とも言います。
現在残っているのはお堀と石垣で、櫓や廊下橋などが復元されています。大分県庁や市役所がお城のすぐそばにあり、城下町として栄えた大分市の面影を残しています。
飫肥城(宮崎県)

飫肥城は戦国時代初期に築城されたと推定され、伊東氏と島津氏の抗争の舞台となりました。その後は飫肥初代藩主の伊東祐兵が、九州征伐の功績として豊臣秀吉から飫肥城が与えられました。
見どころは飫肥杉を用いて再建された大手門や本丸跡へ続く石段です。また、飫肥城下に広がる武家屋敷や石垣が残る町並みは、重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。風情のある町並みをのんびり散策したい場所です。

鹿児島城(鹿児島県)

鹿児島城は初代薩摩藩主の島津家久が、関ヶ原の戦い後の1601年頃から築城を始めた城で、島津氏の居城として江戸時代を通して薩摩藩の政治の中心でした。
見どころは、鹿児島城のシンボルとも言える御楼門で、国内最大級の城門です。門をくぐるとすぐに本丸があります。一見無防備にも見えますが、城の裏側には城山があり、天然の要塞となっています。この背後の城山の形が、鶴が舞っているように見えることから、鹿児島城は別名を鶴丸城とも言います。城山にある展望台からは桜島がよく見えるので、鹿児島観光の際はぜひ行ってみてください。

首里城(沖縄県)

1429年に北山(ほくざん)・中山(ちゅうざん)・南山(なんざん)の3つの国が統一されて琉球王国となりました。首里城は琉球国王が住んでいた城で、1879年に明治政府によって沖縄県の設置が宣言されるまでの約450年もの間、政治や文化の中心地でした。その間、何度か焼失と再建を繰り返しましたが、1945年に沖縄戦で壊滅的な被害を受けました。その後復元されるも2019年の火災で正殿を含む主要な建物が焼失してしまいました。現在復元工事中で、正殿は2026年に復元が完了する予定です。(2025年2月現在)
首里駅から徒歩15分、車の場合は守礼門付近に地下駐車場があります。
中城城(沖縄県)

中城城跡は中城湾を望む標高160mの高台にある城跡です。写真は二の郭で、石垣の上からは、西に東シナ海、東に太平洋、勝連半島や知念半島も見渡すことができます。布積みと呼ばれる石積技法の城郭が曲線を帯びており、目をひく美しさです。

沖縄のグスクの特徴でもある美しいアーチ型の城門は、1853年にペリーが来島した際にエジプト式と評しています。城内には雨乞いの御嶽など八つの拝所があります。
入口から正門まではやや離れていますが、電動カートで正門まで送迎してもらえるので経路順に回ることができます。
今帰仁城(沖縄県)

今帰仁城(なきじんじょう)跡は沖縄本島北部に位置する城跡で、13世紀末頃から築かれ始め、15世紀前半には全長1.5kmの壮大な石垣と10もの曲輪を構える大きな城になりました。1609年に薩摩軍によって攻められ廃城となりましたが、その後も聖域・拝所として存続しました。
城を登っていくと、城郭とその向こうに沖縄の美しい海を望むことができます。この写真は大隅(ウーシミ)を上から見た様子で、戦時に備え馬を養い、兵馬を訓練した場所として伝わります。
那覇空港からは車で1時間40分ほどかかりますが、近くに美ら海水族館や古宇利島があるので、あわせて訪れたいところです。
まとめ
このように九州・沖縄で16ものお城が日本100名城に登録されており、それぞれが固有の特徴をもっているのでとても面白いです。また、100名城のお城にはスタンプが設置されています。スタンプラリーをしながらお城めぐりをするのもいいですね。
 |
日本100名城と続日本100名城に行こう 公式スタンプ帳つき (歴史群像シリーズ) 新品価格 |